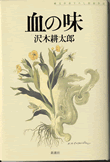 |
|
||||||||
|
血 の 味
|
|||||||||
|
著者
|
沢木耕太郎
|
||||||||
|
出版社
|
新潮社
|
||||||||
|
定価
|
本体 1600円(税別)
|
||||||||
|
|
ISBN4−10−600666−9
|
||||||||
|
第一章 中学三年の冬、私は人を殺した。ナイフで胸を一突きしたのだ。ナイフはBONEというアメ リカ製のもので、刃渡りは八・七センチだった。私がそんな半端な数字をいまでも覚えているの は、逮捕されてから審判にいたる過程で、警察や検察の取調官ばかりでなく、家庭裁判所の調査 官の□からも何度となく出てきたからだ。とりわけ、私に付添人としてついてくれることになっ た初老の弁護士が、センチをサンチと発音するため、しばらくはその「八サンチ七ミリ」という 言葉が耳について離れなかった。刃渡り「八サンチ七ミリ」のナイフは、二つに折るとすっぽり 手に隠れてしまうほど小さかった。そんなナイフで人の命を奮えるとは、実際に自分が刺してし まうまでわからなかった。 警察の留置場から鑑別所にまわされたあげく少年院に送られることになった。鑑別所にいるあ いだはよく刺した瞬間のことを思い出した。少年院に人ってからも、ナイフで胸を刺したときの 感触がまだ手のひらに残っていた。いくら石鹸で洗っても手のひらについた血の脂が残っている ような気がしてならなかったのだ。しかし、少年院を出るころには、無意識に手のひらをズボン にこすりつけているというようなことはなくなっていた。それとともに、夜中に涙を流す夢を見 ることもなくなった。 私は幼いころから泣いた記憶がほとんどない。それは現在にいたるまで変わらないが、少年院 に入ってからはときおり涙を流している夢を見るようになった。その夢の中で、私はいつも砂漠 にいる。砂漠といっても一面にさらさらとした砂が広がる砂漠ではなく、赤ん坊の頭ほどの大き さの石がゴロゴロしている荒れ野だ。私の足元には大きな穴があいており、その横にはうずたか く積まれた土くれがある。それが死体を埋葬するために掘られた穴だということはわかっている のだが、私のまわりのどにも死体が見当たらない。風に土壌が舞う中、私はその穴の前に立ち 尽くし、涙を流している。何が悲しいのか自分にもわからないまま、大きく眼を見開いて、ただ 涙を流しているのだ。あるいは、眠りながら実際に涙を流していたこともあったかもしれない。 朝起きたときに、眼が腫れぼったく感じることが何度となくあったからだ。 少年院には、民間から一種のボランティアとして篤志面接委員という人たちが来ていた。私が 定期的に会うことになったのは街の文具店の経営者だった。努力をすれば道は開けるという強固 な信念を持っているその篤志面接委員は、またおせっかいなほど親切な人でもあった。少年院を 出た私は、その篤志面接委員の世話で、彼の息子の会計事務所に雇ってもらえることになった。 のちに聞かされたところによれば、そんなことが可能になったのも、私が少年院でよく本を読ん でいたからであったらしい。少年院では、中学時代の経歴を知っている教官が私にスポーツをさ せたがった。しかし、私は義務としての運動以外は決してやろうとしなかった。自由時間には本 を読んでいた。手に取ったのは他愛ない娯楽小説ばかりだったが、それでも私を他の非行少年と は違うと錯覚させるくらいの意味はあったらしい。その話を教官から聞かされていた篤志面接委 員は、更生保護施設に入らざるをえなかった私の身元引受人になってくれただけでなく、自分の 息子にその会計事務所で使ってみてくれないかと頼んでくれたのだ。最初に引き合わされたとき、 まだ三十を過ぎたばかりだったその息子の税理士は、私のどこを見込んだのか一種の雑用係とし て雇ってくれた。無口なところがいいと思ったのかもしれない。会計事務所にただひとりいる事 務員は、電卓のキーを叩きながら、のべつしゃべりかけてくるような中年女性だった。 しかし、その会計事務所は居心地のよいところだった。篤志面接委員の息子の税理士も、おし ゃべりな中年の女性事務員も、私に対してさりげない心づかいを示してくれた。私が少年院出だ ということにまったく触れないというのではなく、時には中年の女性事務員がお茶を入れながら、 少年院ではいつお茶を飲むの、などと説くことがあった。私は食事のときだけですと答えながら、 別に不快に思うことはなかった。彼女が素朴な疑問から説いているのがよくわかっていたし、そ うしたことを口にするのも、事務所に私たち三人しかいないときに限られていたからだ。それは また、多少うっとうしくはあったが親愛の情のあらわれと感じられないこともなかった。ただし、 その彼女に、私の犯した罪が殺人だというまでの知識があったかどうかはわからない。 私は事務所と顧客と税務署とのあいだの使い走りから、やがて会計事務の手伝いもさせられる ようになった。入って二年後には大学人学資格検定試験を受けて合格し、その翌年には国立大学 の経営学部の二部に入ることができた。大学在学中に税理士試験の大半の科目に合格しており、 卒業の年には税理士の資格を取っていた。さらにその翌年には公認会計士の二次試験にも合格し た。 少年院を出てから公認会計士の二次試験に合格するまでの九年間は、常に試験勉強に追いまく られる日々だったといってもよい。その間、あのときのことはほとんど思い出さなかった。時と して思い出しかかることはあったが、意志の力で押し止どめる二とができた。私にとってそれは、 すでにシャックリを止めるのと人差ない簡単なことになっていたのだ。、記憶が甦りそうになると、 大きく息を吸ってから息を止め、前方の一点を見つめる。外にいるときなら街路樹の木の梢でも いいし、部屋の中なら目覚まし時計の秒針でもいい。それらをしばらくじっと見つめていると、 シャックリがおさまるようにしだいに思い出す危険が薄らいでいくのだ。私は、少年院での二年 の歳月を代償に、殺人の記憶を封じ込めることができるようになったのだ、と思っていた。 だが、記憶というものはそれほど柔順なものではなかった。公認会計士の正式な資格を得て少 し 時間に余裕ができるようになると、思いもかけない瞬間にあのときのことが甦ってきて私を 狼狽させるようになった。 本文P.4,5,6,7より |
|||
|
BOOKS ルーエ http://www.books-ruhe.co.jp/
・・・・・・HOME・・・・・・
|
|||