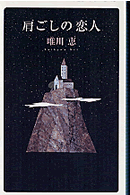
■文学賞
2001年 第126回 直木賞受賞
![]()
女はいつだって、女であること自体が武器だ きっとあなたの中にいる、ふたりの女の物語 ・・《萌》 気に入ってしまいそうなものを見つけた時、必ずいちゃもんをつけたがる、自分にはそんなところがある。もうわかっている。彼は、とてもいいセックスをする。・・《るり子》 私、いつかあなたは私を好きになるような気がするの。だって、私を好きにならない男がこの世にいるなんて、どうしても信じられないんだもの。
|
肩ごしの恋人
|
||
|
著者
|
唯川恵 | |
|
出版社
|
マガジンハウス | |
|
定価
|
本体価格 1400円+税 | |
|
第一刷発行
|
2001/9/20 | |
| ISBN4−8387−1298−7 | ||
|
|
||
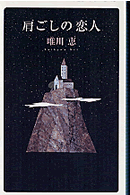 |
■文学賞
女はいつだって、女であること自体が武器だ きっとあなたの中にいる、ふたりの女の物語 ・・《萌》 気に入ってしまいそうなものを見つけた時、必ずいちゃもんをつけたがる、自分にはそんなところがある。もうわかっている。彼は、とてもいいセックスをする。・・《るり子》 私、いつかあなたは私を好きになるような気がするの。だって、私を好きにならない男がこの世にいるなんて、どうしても信じられないんだもの。 |
|
|
1 さらさらとした陽が差し込む窓際の席に、花嫁花婿が神妙な顔つきで立っている。 会場に和やかさが戻る。 青木るり子、いや、結婚したのだからもう室野るり子だ、彼女が純白のウェディングドレス姿で満足そうなほほ笑みを浮かべている。 結婚も三回目ともなれば慣れたものだ。 まったくよくやるものだと呆れてしまう。三回目にもかかわらずこんな大げさなことができるのは新郎の室野信之が初婚だからだ。 れにしても、三回とも招待されたこっちの身にもなって欲しい。 結局、一回着ただけでリサイクルショップ行きになるわけか、とため息がでた。 それにしてもるり子は縞麗だ。 あの顔に何人の男が騙されたことか。 幼稚園で初めて一緒になった時から、不本意ながら、萌はいつもるり子の騎士役だった。 損な役割だとわかっていても、るり子のあの可愛い顔で泣き付かれると、ついイヤとは言えなくなってしまう。 そうして、好きでもない男の子に告白されて困っているとか、友達の付き合ってる男の子が私を好きで三角関係の真っ最中とか、そんな話を聞かされた。 男の子の低レベルにはぐったりしたが、何より、男どもはいったいるり子のどこを見てるのだろう、と呆れてしまう。 だいたいるり子は誰よりも自分が大好きな女だ。 もともと自分を省みるというような高尚な習慣のないるり子は、昨日あったことはすべて忘れる猫科の女である。 ぼんやりしていると、早くもお色直しのために花嫁退場だそうだ。 二回目はカクテルドレス一回分が減った。
|
|||
|
Copyright (C) 2001 books ruhe. All rights reserved. 無断でコピー、転写、リンク等、一切をお断りします。 |
|||