|
|
||
|
著者
|
成田憲彦 | |
|
出版社
|
講談社 | |
|
定価
|
本体価格 2000円+税 | |
|
第一刷発行
|
2002/02/15 | |
| ISBN4−06−211051−2 | ||
|
|
||
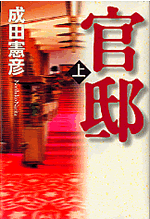 |
日本政治中枢の全真実! 総理が密会した男。その魔手から逃れる道は、1つしかなかった――。 <元総理秘書官が書き下ろした、2400枚、空前の本格政治小説> 官邸と「抵抗勢力」の関係など、現在政治がわかる最高のテキストだ。著者の確かで冷静な眼力は感銘を覚えさせる。――佐々木毅氏(政治学者・東大総長) 当事者しか書き得ない細部描写の圧倒的迫力。この本の衝撃は政治「内幕」ドキュメントの常識を根底から破壊した。――佐野眞一氏(ノンフィクション作家)
|
|
|
「今革命をやろうとしているのに、もう次の革命のことを考えていると感心していた。大変なことだなァ、ともね」「一筋縄でいかないことは、総理も重々分かっています」■「恐いのは、何も発言しないヤツだよ。代議士会や議員総会では、ジーッと聞いているだけのふりをしているヤツらだ」■「裏で左派と手を結んで、政府案を否決させようとしているんだな。最初から参議院に狙いをつけているんだ」「何かこう、地雷原の中を歩いているようだな」■「暗闘のない世界はないよ。逆に言えば、暗闘などというおどろおどろしい言葉を使う必要はないんだ」■「こんな政権は、長続きしないよ。国民は熱病に取り憑かれているだけだ」■「しかしあの常軌を逸したすさまじいばかりの権力への執着心は、学ばないとなあ」「ウチなんか覚めた評論家ばかりだから駄目だ」■「答弁は求めておりませんが。総理、何かご発言がございますか?」■「総理が誰と会おうと、それは総理の自由だ。政治家は裏ではいろんな人間同士が会っているんだからな。政治家の基本的人権みたいなものだし、男と女の密会と同じだよ」 著者紹介
|
|||
|
一 真紅の中央階段 その日の朝、風見透が官邸に着いたとき、閣議はまだ
|
|||
|
|
|||
|
このページの画像、本文からの引用は出版社、または、著者のご了解を得ています。 Copyright (C) 2001 books ruhe. All rights reserved. 無断でコピー、転写、リンク等、一切をお断りします。 |