|
|
||
|
著者
|
||
|
出版社
|
講談社 | |
|
定価
|
本体価格 2000円+税 | |
|
第一刷発行
|
2002/9 | |
| ISBN 4-06-211465-8 | ||
|
|
||
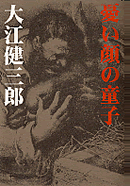 |
滑稽かつ悲惨な老年の冒険をつうじて、死んだ母親と去った友人の「真実」に辿りつくまで。魂に真の和解はあるのか? 書下ろし長篇小説 「森に入って、ある1本の木を選んで、ちょうどいまの年齢の、老年の私が待っている。その私に、子供の私が会いに来るんだ。 しかし老人はね、少年に対して、きみが夢みるほど高い達成はない、この自分が、つまりきみの50年後なんだから、とはいわない。それが「自分の木」のルールだから……」 |
|
|
1 古義人は、幼・少年時に白楊の巨木の餐えていた記憶のある地所を母親から贈られた。 (本文P.11〜13より 引用) |
|||
|